「うちの子、何が好きなのかさっぱり…」
「将来のこと、ちっとも真面目に考えてないように見える…」
こんなお悩み、ありませんか?
子どもの「好き」や「関心」は、実は小さな行動の中に隠れています。
この記事では、一児のパパでもあり、探求教育の現場で多くの高校生と関わってきた私の視点から、親ができる関わり方のヒントとNG行動をお伝えします。
「好き」の芽を見逃さないための親の視点

子どもの好きは、「これがやりたい!」という言葉で出てくるとは限りません。
小さな頃であれば素直に表現してくれることも多いですが、成長と共に難しくなる部分もありますよね。
では親としては、その芽を見逃さないために、何に注目すればいいのでしょうか?
「繰り返す行動」にこそヒントがある
子どもが毎日のようにしている行動、ありませんか?
例えば、いつも同じ音楽を聴いているとか、何気なくイラストを描いているとか。
その「またそれ?」と思うような繰り返しこそ、好きの入り口です。
探求授業の中でも、「なんとなく好きで続けてた」という子が、自分の進路のヒントを見つけていく姿を見てきましたし、私自身も同じような経験をしてきました。
無駄に見えるものほど、好きのタネになる
「役に立つの?」
「将来に関係あるの?」
「いつもいつも楽しいの?」
などと大人は考えがち。
でも、子どもにとっては『意味があるか』よりも『楽しいか』が先なんです。
私たち大人は忘れてしまいがちですが、自分たちが10代の頃はそうだったはず。
親が効率や結果を優先しすぎると、小さな興味の芽を摘んでしまうことも。
まずは「楽しんでるならOK」というスタンスを持つことが大切です。
好きを引き出す親の声かけ

子どもが自分の興味や関心に気づくきっかけは、実は親のひと言だったりします。
世界観に共感したり、声をかけていますか?
ここでは、肯定的な関わり方の具体例をご紹介します。
「それ面白いね」の一言が子どもを変える
このひと言には、子どもを肯定する力があります。
あれ?もしかして、逆のこと言ってしまっていますか?
言いたくなる気持ちも分かりますし、実際忙しかったり余裕がないとつい責めてしまったり否定してしまいます。
今日から少しだけ意識して、子どもを肯定してみましょう。
「それが好きなんだね」
「なんだか面白そうだね」
「ちょっと教えてよ」
このように親から言われることで、子どもは『否定されないんだ』『話しても大丈夫だ』と思えるようになります。
受け入れてもらえると感じることで、自分の好きが育つ環境が整っていきます。
質問で気づきを促す
子どもの興味関心について、親として興味関心を持っていますか?
『あなたのことを見ているよ』と感じさせる質問をしてみましょう。
「どうしてそれに興味あるの?」
「どんなところが好きなの?」
「よく知らないから、教えてくれないかな?」
などと問いかけることで、子ども自身が自分の思考と感情を整理できます。
質問は、相手の興味に寄り添う姿勢でもあります。
コントロールしようとする質問や否定的な言い方ではなく、『あなたの見ている世界を、興味関心を知りたい』という視点で問いかけましょう。
知らずにやってしまうNG行動とは?

良かれと思ってかけた言葉や態度が、子どもの興味をしぼませてしまうことがあります。
場合によっては激しい怒りを表現されたり、数日間無視してくるなんて経験もあるでしょうか。
若いころ、親に対して同じような態度を取ってしまった人も少なくないでしょう。
ここでは、避けたいNG行動を具体的に紹介します。
「そんなことして意味あるの?」はNGワード!
この言葉は、子どもにとって『自分の好きは親に認められていない』と感じさせます。
強い自己否定感にもなり、大人になってからも『どうせ認められない』という思考癖に繋がることも。
また、親子の信頼関係には大きな亀裂が入ってしまうでしょう。
どちらも悪くないのにです。
そんな悲しいこと、避けたいと思いませんか?
意味があるかどうかは後でついてくるもの。
子ども自身の『好き』が芽生えているのであれば、それを否定せずに育てる姿勢が大切です。
「向いてないよ」と決めつけるのもNG!
一見して才能がないように見えるからといって、可能性を否定するのは絶対NG!
実は最初はうまくいかないけれど続けていくうちに成長するという子が多いです。
これは私自身の体験談でもありますが、最初からそつなくこなせていた子が、初期の成長が遅かった子に追い抜かれるという場面は何度も見てきました。
『好き』は続きますから、積み上げた時間やスキルは才能を超えると、私は思います。
親が「あなたには無理」と決めつけてしまうことで、子どもは自信を失い、チャレンジする意欲すら持てなくなってしまいます。
どうせなら「やれるところまでやってごらん」と伝えてあげたいですね!
才能を育てるのは信頼関係から
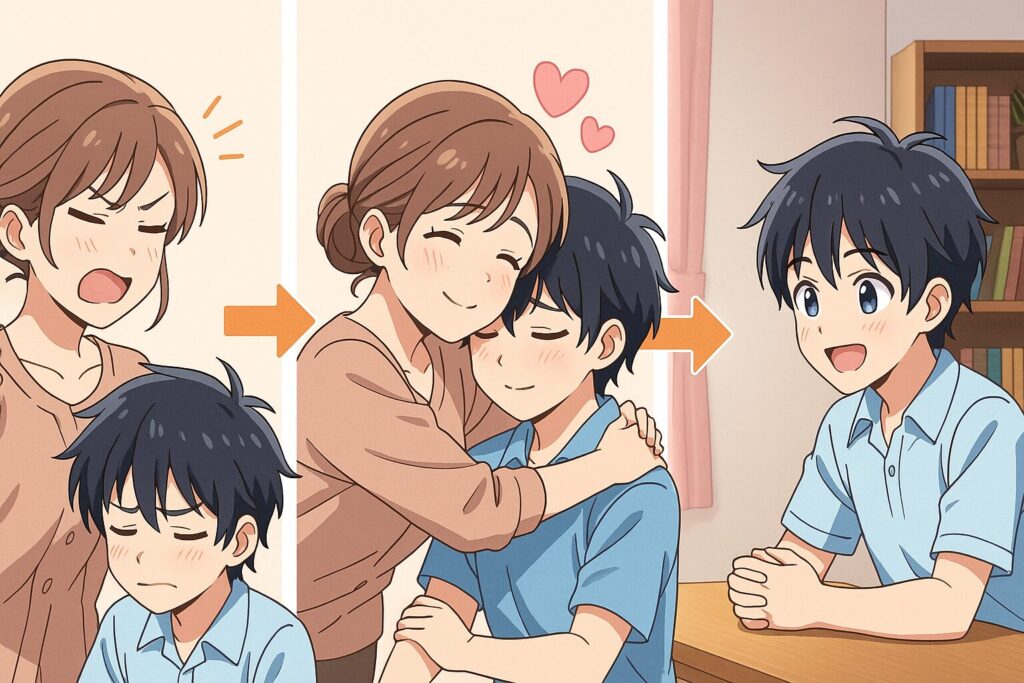
子どもが自分の『好き』を話せるのは、信頼関係が土台にあることが前提条件。
『話してもいい、受け入れてもらえる』と思えば話すし、逆であればほぼ間違いなく話してくれません。
これは大人でも同じですね。
信頼関係は、日常の積み重ねから育ちます。
日常会話の中で感じ取る力を育てる
機嫌や口数の変化に気づいていますか?
多感な時期はちょっとしたことで好不調の波が激しく動きます。
子どもの状態に気づくためには、普段のやりとりが大切です。
一緒に過ごす時間や、ちょっとした会話の積み重ねの中で感じ取りましょう。
「あれ、なにかあった?」と気づいて、優しく聞ける親は信頼されます。
失敗しても、リカバリーが信頼を生む
感情的になって怒りすぎてしまうこともあります。
売り言葉に買い言葉で、子どもと本気で言い合いなんてこともあるでしょう。
その後がめちゃくちゃ大事!
「言い過ぎてしまってごめんね」
「ちょっと嫌な言い方しちゃったね」
と伝えられていますか?
親から先に謝れるか、何事もなかったかのように時間に任せるのか、子どもに謝らせるのか。
私たち親の選択によって、関係は大きく変わります。
悪いなと感じた部分は誠実に謝る、こうした積み重ねが信頼を作るのです。
まとめ

子どもの『好き』は、才能の入口です!
その芽を見逃さず、潰さず、育てるには、親の声かけと信頼関係が何より大切です。
私たちNPO法人LETUSでは、学校での探求授業や生徒個人へのアドバイスを行っています。
ここで培った経験を活かし、やりたいことを見つけるサポートや、親子向けの進路相談も提供しています。
「もっと具体的な関わり方を知りたい」
「子どもとの関係に悩んでいる」
そんな方は一度、問い合わせフォームよりご相談ください。


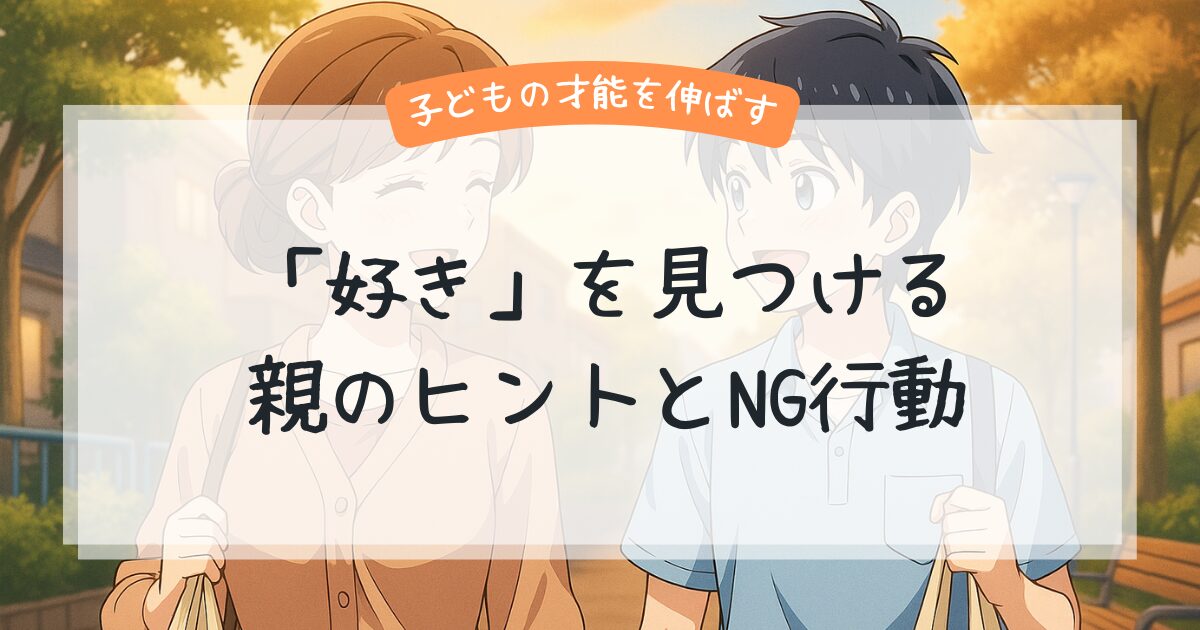
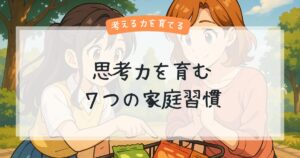
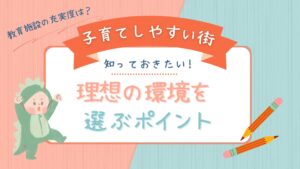
コメント