「学校の成績だけで将来を決めていいの?」と感じたこと、ありませんか?
誰しも『正解』を追い求めてしまう、縛られてしまう傾向があります。
これからの社会で特に必要なのは『正解がひとつじゃない問題』に向き合う力。
この記事では、家庭でできる考える力の育て方について、実体験を交えてご紹介します。
なぜ今、考える力が求められているのか?
少子化やAIの進展によって、これからの社会は『自分の頭で考えて動ける人』が求められる時代。
偏差値や正解だけを追い求める教育では、社会で生きる力が育ちにくくなっています。
このセクションでは、なぜ今『考える力』が大切なのかを、学校現場や地域活動の事例を通してお伝えします。
正解主義の限界と、社会で求められる力の変化

かつての私もそうでした。
学校では『テストで100点を取る=正解』という成功体験が刷り込まれていて、分からない問題に出くわすたびに不安になったものです。
不安を通り越し、常に怒りすら感じていました。
でも実際の社会は、正解がない場面だらけ。
地域の課題や仕事の現場では、「どんな行動を選ぶか」や「人とどう関わるか」が重視されます。
私たちが関わる探求型授業では、正解を与えるのではなく、生徒自身に問いを立ててもらうことで、主体的な思考力が育まれていきます。
考える力がある子は、親の問いかけで育つ

考える力が豊かな子にはある共通点があります。
それは『家庭で問いかけをされている』回数がとても多いこと。
どうでしょう?お子さんに対して、親目線での正解を押し付けてしまっていませんか?
私自身も、予定が詰まっていたり心に余裕がないときは、つい「いいから、〇〇しなさい!」と言ってしまうため、反省です。
「あなたはどう思う?」という一言を、意識してみましょう。
親からの問いかけが、子どもの思考のスイッチを押すんです。
「間違ってもいいんだよ」
「あなたの意見を聞かせて」
と伝えることで、正解を気にせず自由に考える癖がつきます。
親のちょっとした声かけが、子どもの未来の土台をつくるんですね。
家庭でできる「考える力」の育て方とは?
子育て中の親にとって、「考える力を育てたい」と思っても、何をすればいいかわからないこともあるでしょう。
ここでは、家庭でできるシンプルな工夫を5つご紹介します。
今日からでも取り入れられる内容ですから、気に入ったものからやってみてください。
親自身が考えている姿を見せる

「ママ(パパ)も、まだ答えが出ないけど、今はこういうふうに考えているよ」と言葉にして伝えてみましょう。
子どもは、考えることそのものに親しみを持てますし、同じように考えを伝えてくれることもきっと増えます。
親の迷っている姿も子どもにとっては学びになりますし、『迷う=悪いことじゃない』という安心感にも繋がりますね。
「決めさせる」体験を日常に取り入れる

我が家の事例ですが、娘に決めてもらう練習をしています。
「今日の夕飯、何にするか任せるから決めていいよ」
「予算は2人で4,000円くらいで、どうする?」
など、小さなことでも自分で決める体験が、考える力を育てると実感しています。
自分で考えて決める→結果を体験する→成功体験や失敗体験を経てまた考える、という好循環が自然に生まれます。
「どうしてそう思ったの?」を意識的に使う

これ本当にやってしまっていたのですが、子どもの発言に対しての適当な返事はNGです。
「へぇ〜、そうなんだ」
「分かったからとりあえず今は早くご飯食べて」
「後で聞くから」
など、やってしまいがちですが、子どもの考えに耳を傾ける癖をつけていきましょう。
「なるほど、どうしてそう思ったの?」と、子どもの目に映っている世界観に一歩踏み込むことで、思考が深まります。
言語化して伝えるスキルも同時に身に付きますからね。
大切なのは、途中で遮ったり急かしたりしない、否定せずに聞き切ること。
親が興味を持って聞く姿勢は、子どもに「自分の考えを持っていいし、伝えていいんだ」という安心感を与えます。
答えよりも、一緒に考える時間を
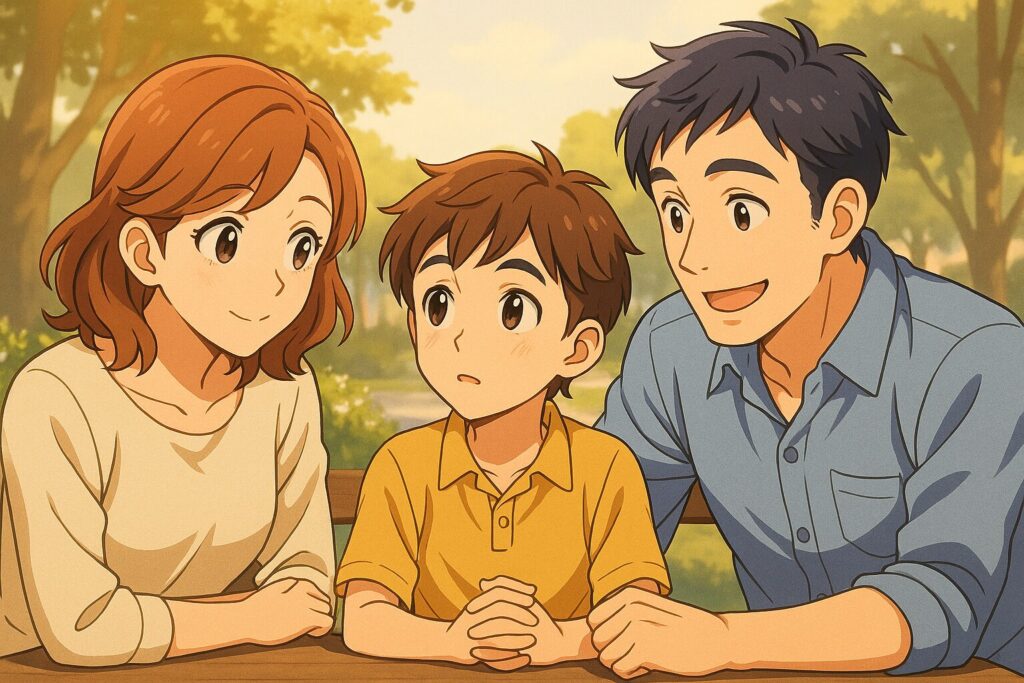
「どうしたらもっと面白くなるだろう?」
「他にどんな方法があるかな?」
「最高の晩ごはんメニューを考えてみない?」
など、絶対的な正解のない問いかけは思考力や探求心を育てます。
正解がないテーマだからこそ、親子で一緒に考える時間そのものを楽しめますし、やってみると子どもの方が自由で柔軟な発想を提案してくれることも少なくありません。
映画やアニメの感想を共有する

これは本当に、子どもは結構語ってくれます!
「どこが一番印象に残った?」
「次回作(アニメなら、次の展開)どうなると思う?」
「どの登場人物(キャラ)が好き?」
などと聞くことで、作品そのものを一緒に味わう時間が生まれます。
正解のない問いを楽しむ練習になりますし、世界観の共有によって親子の信頼関係も深まります。
視点をズラす質問をしてみる
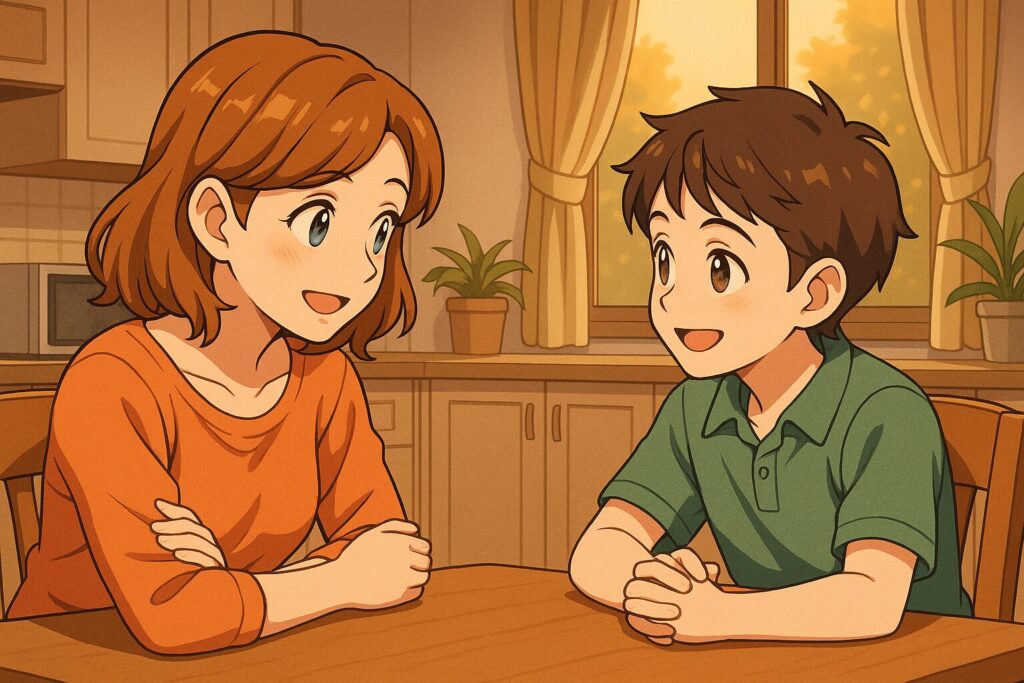
親子だからぶつかることもあるでしょう。
意見や感情が出てきたときには、お互いに視点をズラしてみることで理解が深まります。
「ママ(パパ)はどんな気持ちになったと思う?」
「あなたの気持ちに立って考えてみるね」
こういった視点を変える問いかけを入れると、意外と冷静になれます。お互いにです。
このような視点をズラす癖をつけることで、主観的な意見だけにとらわれない、柔軟な思考力や想像力が育ちます。
偏ったの見方に縛らない、他者理解や論理的思考にもつながります。
親子レッスンに参加してみる

忙しくて家庭内ではなかなか話せない…
そんなときこそ、外部の力を活用しましょう。
親子で参加できる探求型ワークショップもご用意しておりますので、「子どもと一緒に参加したい」という方は問い合わせフォームよりご連絡ください。
家庭の外にある対話の場が、親子にとっての新しい発見の場になるはずです。
まとめ
正解だけを追う時代は終わりつつあります。
これからは『自分で問い、考え、選ぶ力』が求められる時代。
そんな力は、家庭での声かけや日常のやりとりから育まれます。
私たちNPO法人では、学校での探求授業や地域イベントを通じて、こうした力を育てるサポートをしています。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。


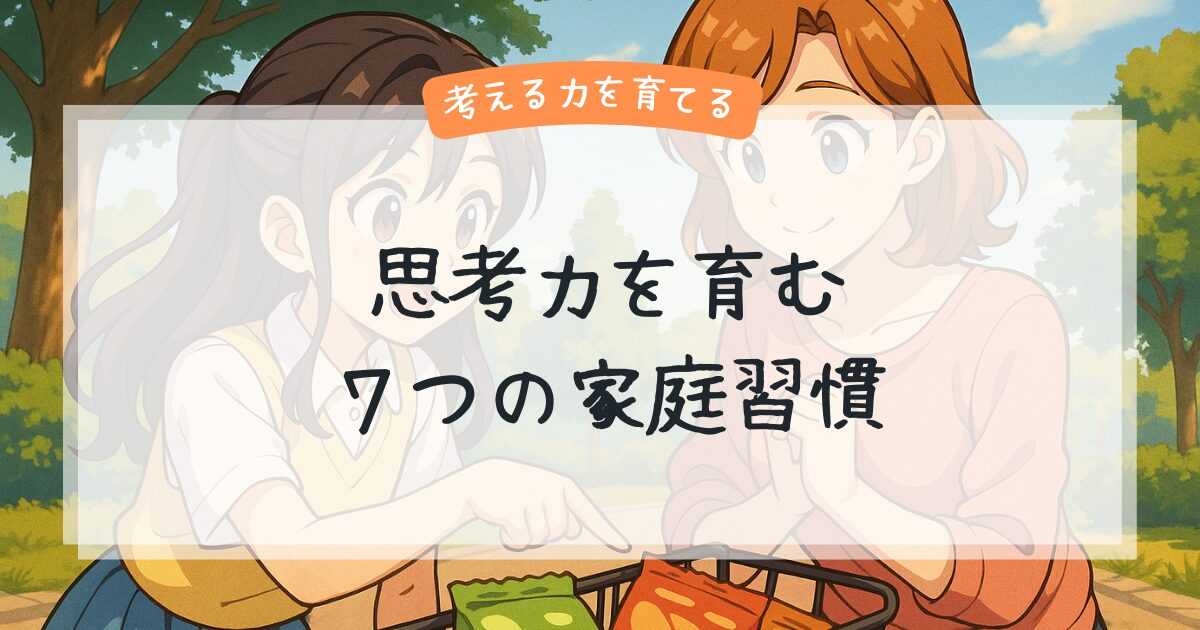
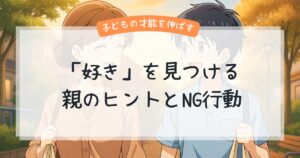
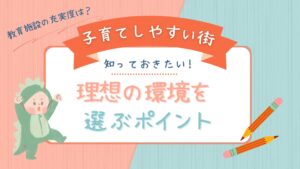
コメント